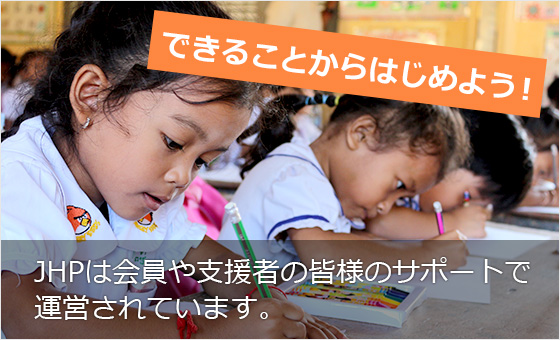学校ができるまで

調査開始から校舎、井戸、トイレ棟完成まで半年から1年の期間がかかります。
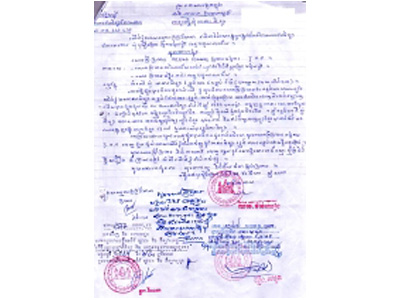
1.各地域・学校からのリクエストレターの受理
「校舎が古くて倒れそう」「教室数が足りない」「校舎がなくて青空教室で授業をしている」など、カンボジア各地の学校から鉄筋コンクリ造の校舎建設の要望がプノンペン事務所に送られてきます。

2.学校の現状調査
リクエストレターの中から緊急性の高い何校か選び、実際に現地へ赴いて現状を調査します。学校関係者だけでなく、校区の地域住民にもインタビューして、優先順位を決めます。

3.地域住民との建設前協議(地域の協力体制などの確認)
学校は子どもたちのためだけでなく、地域のためにあります。なるべく地元業者を雇用するために、建設前協議では学校・地域住民の協力がどれくらい得られるかを確認し、新校舎の建設場所、建設後の維持・管理に関しても話し合います。

4.建設開始
建設資金を提供してくださる支援が決まり、いよいよ工事開始です。

5.床施工
床施工は校舎を長く使ってもらうために重要な工程です。雨期のあるカンボジアで建物を長持ちさせるには、川沿いや洪水・浸水などの被害を受けやすい地域では、高床にする場合もあります。

6.柱・壁施工
土台が出来上がったらコンクリートの柱と、レンガを積み上げ壁の施工に入ります。新しい校舎は雨期でも教室に雨が入ってくることはありません。

7.屋根施工
校舎がだんだん形を現わしてきました。屋根は瓦葺きです。青空教室も楽しかったけれど、屋根があれば安心して勉強ができます。

8.完成
トイレ棟、井戸も同時にできあがりました。子どもたちの勉強だけでなく、生活に必要な設備が整いました。活動隊が作ったブランコでさっそく子どもたちは遊んでいます。

9.贈呈式
ドナーさんも出席しての贈呈式です。カンボジアに滞在中の活動隊もソーラン節を披露して、盛大に式典が行われます。

10.定期的に視察
JHP・学校をつくる会では、寄贈した後も定期的に校舎のメンテナンスの助言を行っています。校舎には子どもたちだけでなく、地域住民、資金を提供してくださったドナーさんの思いも詰まっています。いつまでも長く使ってほしいと考えています。